愛犬と暮らす日々は癒されるけれど、「部屋が犬臭いかも…」と感じたことはありませんか?
特にマンションは換気がしにくく、体臭やトイレの臭いがこもりやすいものです。
本記事では、匂いの原因から対策方法、人気の消臭アイテムやおすすめ空気清浄機まで、わかりやすく解説します。
当サイトで紹介する商品は、料金や機能性・デザイン性など様々な条件から紹介しています。なお、みなさまに無料コンテンツを提供する目的で、複数のアフィリエイトプログラムに参加し、手数料の支払いを受けていることをご了承ください。
犬と暮らす上での臭いの悩み
犬との生活は癒しや楽しみがある一方で、「部屋が臭う」と感じる瞬間も少なくありません。
特に室内で飼っている場合は、犬の体臭やトイレのニオイ、グッズに染みついた汚れなど、さまざまな原因から匂いが発生します。
ペットの匂いが部屋にこもってしまうと、飼い主自身は慣れて気づかなくても、来客には不快に感じられる可能性もあります。
マンション特有の悩み
マンションで犬を飼う場合、戸建てに比べて「臭いがこもりやすい」「音や匂いで近隣トラブルになりやすい」といった独自の課題があります。
換気しにくい間取り
マンションの多くは気密性が高く、窓の数も限られているため、換気がしづらいという特徴があります。
そのため室内でペットを飼っていると、トイレのアンモニア臭や体臭が空気中に滞留し、徐々に部屋に染み付いてしまうことも少なくありません。
特に湿度が高い日や、雨で窓が開けられない日は、より雑菌の繁殖に注意が必要です。
匂いでの隣人トラブルの可能性
ペット可物件であっても、隣人との壁は一枚。
ペットのトイレ臭やシャンプー後の湿った香りなどが換気口や共有廊下に漏れると、苦情の原因になる可能性があります。
また、マンションでは共用部分の使用ルールも厳しく、エレベーター内での体臭や被毛のニオイが問題視されるケースも。
トラブルを未然に防ぐためにも、臭い対策は“自分のため”以上に“周囲のため”でもあります。
犬の匂いの主な原因
犬の匂いと一言でいっても、その発生源は多岐にわたります。
単に「犬臭い」と感じるだけでなく、どこから、どのような臭いが出ているのかを特定することで、適切な対策が可能になります。
体臭(よだれ、耳、肛門腺、口臭)
犬の体には人間にはない「アポクリン腺(脂腺とつながった汗腺)」が全身にあり、ここから分泌される皮脂や汗が空気に触れて酸化することで独特の体臭が発生します。
さらに、耳の中は湿気がこもりやすく雑菌が繁殖しやすいため、外耳炎などの病気によって匂いが強くなることがあります。
肛門腺から分泌される液体も臭いが強烈で、たまると臭い以上に破裂や感染症のリスクにもなります。
また、歯垢や歯石の蓄積による口臭も見落とされがちです。これらの箇所は定期的にチェックし、ブラッシングや拭き取りで清潔に保つことが大切です。
排泄物
排泄物は室内飼いの犬におけるニオイの最大要因です。
尿にはアンモニア、便には硫化水素やスカトールといった強烈な臭い成分が含まれており、時間が経つとその匂いはさらに悪化します。
とくにシートを長時間交換しなかった場合や、トイレの縁からこぼれてしまった場合には、床やカーペットにニオイが染み込むことも。
適切なトイレシートの選び方や、すぐに処理できる習慣が大切です。
病気からくる場合も
通常の匂いとは異なる強い異臭を感じた場合、それは病気のサインかもしれません。
例えば、内臓疾患により口臭がアンモニア臭に変化したり、皮膚病で被毛から異常な臭いが発生したりするケースがあります。
肛門腺が炎症を起こすと、膿のような匂いが漂うこともあります。
飼い主が日々のケアで早めに気づくことが重要で、異常な匂いに気づいたらすぐに動物病院で相談するようにしましょう。
匂いの元となるもの
部屋の中には、知らず知らずのうちに犬の匂いが蓄積してしまうアイテムや場所がたくさんあります。
ここでは、生活の中で見落としがちな“臭いの溜まり場”を紹介します。
わんちゃん自身
当然ながら、犬自身が匂いの発生源です。被毛に皮脂がたまった状態で放置すると雑菌が繁殖しやすく、さらにニオイが強くなります。
濡れたままの被毛も同様で、生臭い臭いの原因になります。
シャンプー後は必ずタオルとドライヤーで乾かし、皮脂や雑菌が繁殖しないよう心がけましょう。
排泄物入れからの匂い
トイレで使用したシートや便をそのままゴミ箱に入れておくと、悪臭の原因になります。
特にフタのないゴミ箱は要注意で、臭いが部屋全体に広がってしまうこともあります。
消臭機能付きゴミ箱や、防臭袋の使用が有効です。
布製品や家具
ソファやカーテン、クッションなどの布製品はニオイを吸着しやすく、犬のよだれや体臭、汚れた被毛から発生する臭いが染み込みます。
特にソファカバーやクッションカバーは週に1回の洗濯を目安にしましょう。
ペット用の布用消臭スプレーを併用すると効果的です。
床材への蓄積
犬が歩く床には足裏の汗や排泄物の跳ね返りが付着し、ニオイの蓄積源になります。
フローリングは雑菌が繁殖しづらいものの、木目に尿が入り込むと消臭が難しくなります。
定期的に拭き取り、清潔を保ちましょう。
換気不足や湿度など
空気の流れがない部屋では、犬の匂いが滞留しやすくなります。
さらに湿度が高いと雑菌の繁殖が進み、匂いが強くなる原因に。除湿機や空気清浄機を設置し、空気を循環させることで臭いを軽減できます。
臭いを無くす方法3選
臭いの発生を抑えるためには、日頃からペットの臭いがつきにくいように気を付けることが必要です。
そこで、自宅でできる愛犬の匂い対策についてご紹介します。
1番大切なのは掃除と洗濯
臭い対策の基本は、こまめな掃除と洗濯の習慣づけにあります。
部屋の隅やトイレの周囲、犬がよく寝そべるラグやソファなどには皮脂汚れや雑菌が溜まりやすく、ニオイの発生源となります。
フローリングにはクエン酸スプレーを活用し、布製品は月1回以上の洗濯を目安にしましょう。
また、カーテンやクッションなど大きな布製品には、ペット用消臭スプレーを使って除菌・消臭をセットで行うと効果的です。
拭き掃除にはタオルやシートを使い、使い捨てタイプを選べば雑菌の繁殖も防げます。
愛犬の体のケアを習慣にしよう
犬自身が清潔であることは、部屋全体のニオイ軽減に直結します。
特に被毛にたまった皮脂や湿気、汚れは、臭いの原因になりやすいため注意が必要です。
月に1〜2回のシャンプーを基本とし、間の日にはウェットタオルで体を拭くと良いでしょう。
耳の中や肛門腺の手入れも忘れずに。
耳の奥にたまった耳垢は独特のニオイを発しやすく、また肛門腺の分泌物も強烈な臭いを放つため、月1回のケアが推奨されます。
日常のブラッシングで抜け毛や汚れを除去することも、体臭を抑える効果があります。
消臭アイテムを上手に活用
掃除やケアと並行して活用したいのが、消臭グッズの導入です。
スプレータイプ、シートタイプ、置き型タイプといった様々なタイプが販売されており、それぞれ使用シーンに合わせて選ぶのがポイントです。
例えば布製ソファにはスプレー、床掃除には除菌消臭シート、トイレのそばには置き型の消臭剤がおすすめです。
製品を選ぶ際は、天然成分で構成されており、万が一舐めても安心なものを選ぶとより安全です。
また、部屋全体の空気中に漂うニオイを取り除くには、空気清浄機の活用が非常に有効です。
とくに気密性の高いマンションでは、空気がこもりがちになるため、臭いが抜けにくくなります。
脱臭フィルター付きの空気清浄機を使えば、トイレのアンモニア臭や体臭由来のニオイ成分を除去できます。
排泄物の匂い対策
犬のトイレ周りのニオイは強烈で、放置すると室内全体に広がることもあります。
特に尿に含まれるアンモニア成分は、時間が経つほど空気中に拡散されやすくなるため、排泄物の匂いを効果的に抑えることが重要です。
専用のゴミ箱を使用
排泄物を一般的なゴミ箱に入れると、蓋を開けた瞬間に強烈なニオイが広がることがあります。
ペット用に設計された密閉型の専用ゴミ箱を使用すれば、臭いの拡散を防ぎ、衛生面も安心です。
中には脱臭カートリッジを搭載したモデルや、ゴミ袋ごと密封してくれるタイプもあり、非常に便利です。
消臭剤を使用する
排泄物の処理後には、専用の消臭スプレーを床やトイレトレーに使用することで、臭い残りを大きく軽減できます。
スプレーは植物由来の成分をベースにしたものや、オゾン水を使った製品が人気で、愛犬にも安心です。
また、除菌作用も備えたタイプを選べば、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。
排泄物はこまめに処分しよう
使用済みのトイレシートや排泄物は、可能な限りその都度処分しましょう。
長時間放置すると、臭いが部屋に染みついてしまうだけでなく、菌が繁殖して健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
忙しいときでも1日1回は処理をする習慣をつけると、ニオイの蓄積を防げます。
トイレに流す
愛犬が固形物をした場合は、トイレに流せるタイプの処理方法を取り入れるのも1つの手です。
市販されている流せる袋を使えば、匂いが残る前にすばやく処分できます。
ただし、排水管を詰まらせないよう、一度に大量に流すのは避け、使い方の注意点を守ることが大切です。

床の匂い対策
床は、犬の足裏から出る皮脂や排泄物の飛び散りによって、ニオイが蓄積しやすいポイントです。
見た目はきれいでも、実際には臭い成分が染み込んでいるケースも少なくありません。
ここでは床材に合わせた3つの対策方法をご紹介します。
フローリングはクエン酸とスプレーで
フローリングには尿がしみ込みやすいため、クエン酸スプレーを活用して中和するのが効果的です。
アンモニアはアルカリ性なので、酸性のクエン酸で拭き取ることで消臭効果が期待できます。
使用後は水拭きをしてから乾拭きし、湿気を残さないようにしましょう。
週1回の定期ケアを心がけると、雑菌の繁殖も抑えられます。
カーペットは熱湯&中性洗剤がいい
カーペットは繊維の奥までニオイ成分が染み込むため、表面だけの掃除では足りません。
オシッコなどの汚れがある場合は、まず熱湯を注ぎ、汚れを浮かせてから中性洗剤で叩き洗いをします。
仕上げに水拭きし、完全に乾かすことが重要です。乾燥が不十分だとカビや再発臭の原因になります。
ペット対応カーペットを選ぶ
最初からペット対応のカーペットを選ぶことも、匂い対策には有効です。
防臭・防汚加工が施された商品は、汚れが染み込みにくく、日常の掃除も簡単に済みます。
また、洗えるタイプや部分取り換えが可能なパネル型などもあり、ライフスタイルに合わせて選べます。
ペットグッズのお手入れ
犬の匂いは、意外な場所からも発生しています。
特に日常的に使っているグッズには、体臭やよだれ、皮脂の汚れが蓄積しやすく、放っておくと強烈なニオイを放つ原因に。
ここではグッズ別に適したお手入れ方法をご紹介します。
服やおもちゃはこまめに洗おう
犬用の服やぬいぐるみ、ロープトイなどは、直接体に触れる分、体臭や唾液の汚れが付着しやすいアイテムです。
月に数回、洗濯機で洗える素材であれば、洗剤でしっかり洗いましょう。
おもちゃは煮沸消毒や、中性洗剤を使って手洗いするのも効果的です。
洗浄後はしっかり乾かすことで雑菌の繁殖も防げます。

大きなケージは拭いて消臭
ケージやクレートなどは見落としがちですが、長時間犬が過ごす空間であるため、匂いが蓄積しやすい場所です。
定期的にキッチンペーパーや使い捨てタオルで拭き、ペット用の消臭スプレーを使って除菌・消臭を行いましょう。
床材のマット部分も取り外して洗えるものを選ぶと清潔を保ちやすくなります。
トイレトレーは入念に
トイレトレーは犬が毎日使う場所であるため、最も雑菌が繁殖しやすく、強い臭いの原因にもなります。
使用直後は一見きれいでも、目に見えない尿の飛び散りやシートの汚れが蓄積し、時間が経つほどにアンモニア臭や湿気臭が部屋中に広がる恐れがあります。
掃除は「トイレシートを替えるだけ」でなく、トレーの縁や裏側まで入念に拭き取り、消臭スプレーや除菌スプレーを使って清潔を保ちましょう。
除菌成分のあるペット用クリーナーや、弱酸性のクエン酸スプレーを使うと、臭いの原因となるアルカリ性の汚れにも効果的です。
ソファ・クッションへの臭い対策
犬がくつろぐ時間の長いソファやクッションは、知らず知らずのうちに被毛や皮脂、よだれが染み込み、強烈な匂いの元となります。
見た目は清潔でも、実際にはニオイ成分が蓄積していることが多く、部屋の空気全体に悪影響を及ぼします。
以下のような対策で、快適なリビング空間を保ちましょう。
洗えるカバーを使おう
布製のソファやクッションには、洗濯可能なカバーを使用するのが好ましいです。
被毛や皮脂の汚れが付着したままのカバーを放置すると、雑菌が繁殖して臭いが悪化します。
そのため取り外して丸洗いできるカバーなら、定期的に洗濯することで常に清潔な状態を維持できます。
選ぶ際は、速乾性・防臭加工のある生地を選ぶとお手入れも簡単です。
月1回は洗濯+消臭スプレーを
カバーの洗濯は最低でも月に1回が目安です。
洗濯後には乾いた状態で布用のペット用消臭スプレーを使用すると、香りが残らず清潔感のある仕上がりになります。スプレータイプの消臭剤は、成分が舐めても安心なものであるかを事前に確認しましょう。
また、洗濯が難しい本体部分は、アルコールフリーの布用除菌シートで定期的に拭き取ることも効果的です。
忘れがちなカーテンの臭い
カーテンは部屋の大部分を覆う布製品でありながら、臭い対策が見落とされがちな場所です。
犬の毛や皮脂、空気中に漂う匂い成分が繊維に吸着し、長期間放置すると染みついた臭いが部屋全体を包んでしまうこともあります。
こまめな対処が部屋の空気を清潔に保つポイントです。
洗えるカーテンはシーズンごとに洗濯
カーテンは季節の変わり目ごとに洗濯するのが理想です。
洗濯表示を確認し、洗濯機で洗えるタイプであれば、ネットに入れて弱水流で洗い、よく乾かしてから再び設置しましょう。
香り付き柔軟剤は犬の嗅覚にストレスとなる可能性があるため、無香料の洗剤を使用すると安心です。
布用スプレーを使用
日々のメンテナンスには、ペット用の布用消臭スプレーを使いましょう。
特に犬が寝る場所の近くにあるカーテンは、被毛や皮脂が付着しやすく、強い臭いの原因になります。
数日に一度、表裏にまんべんなくスプレーすることで、清潔感を維持しやすくなります。
消臭作用のあるものも
最近では、消臭機能付きのカーテンや防臭加工が施されたファブリックも登場しています。
初期費用はかかりますが、臭いが気になる家庭では大きな効果が期待でき、長期的には洗濯頻度や消臭剤のコストも削減できます。
室内飼いが前提の家庭には特におすすめのアイテムです。

自宅でできるの体臭のケア
犬の体臭は、皮脂、唾液、被毛の汚れなどが原因で発生します。
定期的なケアを怠ると、体表で雑菌が繁殖し、部屋中に強烈な臭いが広がってしまいます。
ここでは自宅でできる、簡単かつ効果的な体臭ケアの方法を紹介します。
シートや流さないシャンプーの活用
外出やシャンプーが難しい日には、ペット用のウェットシートや流さないドライシャンプーが便利です。
顔周りやお尻周り、足の裏など汚れが溜まりやすい部分を拭くだけでも、ニオイの軽減に効果があります。
使用する製品は無香料で、天然由来の除菌・消臭成分を含むものがおすすめです。
シャンプーの頻度と注意点
犬のシャンプーは月に1〜2回が目安ですが、頻度が多すぎると皮膚が乾燥して逆に体臭が強くなることも。
使用するシャンプーは犬の肌に優しい弱酸性タイプで、洗い残しや生乾きがないよう、しっかりとすすぎ、ドライヤーで完全に乾かすことが重要です。
耳・肛門腺のケアも忘れずに
耳や肛門腺は、見逃しがちな体臭の発生源です。垂れ耳の犬種や長毛種は耳の中が蒸れやすく、雑菌が繁殖しやすい傾向があります。
肛門腺は月に1回程度、絞るか、トリマー・獣医にケアを依頼するのが安心です。
異常な匂いがする場合は、病気の可能性もあるため、早めに診てもらいましょう。
ブラッシングも効果的
日々のブラッシングは、抜け毛の除去とともに、皮膚の汚れや皮脂を取り除く効果もあります。
被毛に付いたほこりやゴミを取り除くことで、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔を保てます。
スキンシップの一環としても役立つため、毎日の習慣に取り入れましょう。
歯磨きは病気の予防にもなる
犬の口臭の多くは、歯垢や歯石の蓄積によるものです。
人間よりも歯周病になりやすいため、歯磨きは週に2〜3回以上行うことが推奨されています。
専用の歯ブラシやデンタルガム、スプレーなどを活用して、無理なく続けられる方法を探しましょう。
口臭が急に強くなった場合は、内臓の病気の可能性もあるため、動物病院での診察をおすすめします。
消臭グッズを使うときの正しい選び方
消臭グッズを使えば、掃除や体のケアと合わせてさらに効果的に匂い対策が可能になります。
ただし、選び方を誤るとペットの健康に悪影響を与えるリスクもあるため、ポイントを押さえて使うことが大切です。

舐めても安全なものを使用
犬は自分の体を舐める習性があるため、床や家具に使う消臭スプレーは「ペットが舐めても安全」と明記されている製品を選びましょう。
天然由来成分や食品添加物由来の除菌剤など、安全性が確認された製品は飼い主にも安心です。
香りの強さに注意
香り付きの消臭剤は一見効果的に思えますが、犬の嗅覚は人間の約100万倍と言われており、強すぎる香りはストレスの原因になります。
無香料、または微香タイプを選ぶと良いでしょう。消臭効果は香りではなく、成分の分解力に注目するのがポイントです。
置き型タイプは誤飲に注意
置き型の消臭剤はペットの手が届かない場所に設置しましょう。
興味本位で噛んでしまい、誤食につながる事例も報告されています。
ケージの外や、家具の上など、犬が届かない高い場所に置くことで事故を防げます。
手作りだと節約&エコにも
重曹やコーヒーかす、木炭などを使った手作り消臭アイテムも人気です。
たとえば、重曹を小皿に入れて棚の上に置いておくだけでも、空間の消臭に効果があります。
使い終わった紅茶葉や炭を乾燥させ、布袋に入れて使う方法もおすすめです。
空気清浄機・脱臭器の選び方
部屋全体の臭いを改善するためには、空気清浄機や脱臭器の導入が非常に効果的です。
特にトイレ臭や体臭が気になるマンションでは、空気の循環と脱臭が同時にできる製品を選ぶことが、快適な生活空間の第一歩となります。
ペット用消臭機能があるものを
近年はペット専用の空気清浄機も登場しており、犬の体臭やアンモニア臭を除去できる脱臭フィルターを搭載したモデルが人気です。
ペットの毛やフケをキャッチするHEPAフィルターを備えたものもあり、アレルギー対策としても有効です。
壁への取り付け型ならトイレ上に最適
限られたスペースでも設置しやすい壁掛け型の空気清浄機は、トイレ周辺に最適です。
常に上から空気を吸引・浄化するため、臭いがこもるのを防ぎ、快適な環境を保つことができます。
配線も目立たず、インテリアにもなじみやすいデザインが多いです。
お手入れ簡単なものを選ぼう
空気清浄機はフィルターの交換や掃除が必要なため、メンテナンスのしやすさも重要な選定ポイントです。
掃除機で簡単にホコリが取れる構造や、交換頻度が少ないタイプであれば、忙しい主婦でも手軽に使い続けられます。
万策尽きたらプロに相談を
掃除・ケア・グッズ対策をしても臭いが完全に消えない場合は、プロのハウスクリーニング業者に依頼するのもひとつの方法です。
ペット臭に特化した脱臭処理を行ってくれる業者では、オゾン脱臭や高圧スチームで床・壁紙に染み込んだ臭いまで除去してくれます。
料金は部屋の広さに応じて変動しますが、費用対効果は高く、リセット効果も抜群です。
業者を選ぶ際は「ペット臭対応可」と明記のあるサービスを選ぶと安心です。
匂いゼロ!来客OKのおうちを目指して
「犬がいるのに臭わない家」は、ちょっとした日常の積み重ねで実現できます。
掃除、消臭グッズ、空気清浄機、そして愛犬のケア。
それぞれを無理なく続けることで、あなたの家はいつでも来客を迎えられる「清潔で快適な空間」へと変わります。
匂いのない空間は、家族にとっても愛犬にとっても、心地よく安心できる場所になります。
今日からできることから始めて、“犬がいるのに素敵な香りがする家”を目指しましょう!
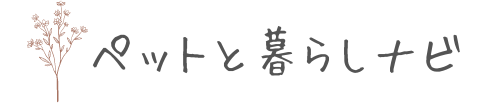

コメント